オカルトマニアクスをフォロー
最強の呼び声高き剣、「ウルフバート」
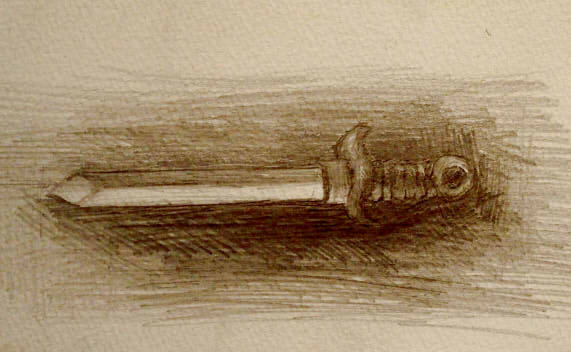
西暦で言えば1000年代頃、スカンディナヴィアのヴァイキングたちが用いたとされている。
拵えは比較的シンプルな両刃の片手剣。
パッと見ただけでは、他の剣との差異は殆どない。
あるとすれば刀身に刻まれた“+VLFBERH+T”(ウルフバート)という銘らしきものだけだ。
しかしこの実にシンプルな剣は、作られた時代において「最強」とさえ呼ばれ、ヴァイキングたちの伝説、武勇と名声に花を添えるがごとく今でも語り継がれている。
ウルフバートの起源
ウルフバートの起源については明確にされていませんが、一般的には古代北欧神話に登場する英雄、ジークフリート(またはシグルズ)が使用した剣とされています。ただし、実際に存在した剣であるかどうかは不明です。
また、製造時期や製作者についても不明な点が多く、正確な情報は存在しません。
ウルフバートの神秘的な力について
ウルフバートが何らかの神秘的な力を持っているとされていることについては諸説がありますが、具体的にどのような力があるのかについては明確な証拠はありません。以下は一般的に伝えられている説明です。
一説によれば、ウルフバートは持ち主の力を増幅する力を持っており、また、不死や永遠の命をもたらすとされています。
ウルフバートは戦いにおいて常に勝利をもたらす剣であるとされています。
また、ウルフバートを持つ者は、不死身であり、病気になることがありません。
さらに、ウルフバートには呪いをかけることができ、敵を呪って死に至らしめることもできるとされています。
また、ウルフバートは持ち主を守護する力があるとも言われています。
これらの神秘的な力は、ウルフバートを製造した鍛冶職人が、秘伝の技術や呪術を用いて作り上げたものとされています。しかし、現代の科学技術では解明できない部分が多く、謎に包まれたままです。
また、戦闘においては、その切れ味や威力が通常の剣と比べて圧倒的に高いとも言われています。
別の説では、ウルフバートは炎を操る力を持っており、炎を纏った剣として描かれることがあります。
また、ウルフバートは「剣の鍛冶神」とも呼ばれており、鍛造技術や魔法的な力を持っているとされている場合もあります。
しかしながら、これらの説はあくまで神話や伝承からの解釈であり、実際にウルフバートがこれらの力を持っていたかどうかは不明です。
最強の剣の伝説と失われた鍛鉄技術
ウルフバートの鍛鉄技術については正確な情報がなく、諸説あります。一体、この剣は他と何が違うのだろうか。
答えもまたシンプルだ。
鉄の純度が違うのである。
一般的には、ウルフバートは非常に高度な鍛鉄技術で作られたとされています。
具体的にどのような技術が使われたかは不明ですが、ウルフバートは非常に硬く、鋭利であり、決して錆びたり腐食したりしないと言われています。
また、ウルフバートは熱処理され、高温の火の中で焼かれたとも言われています。
しかし、これらの情報はすべて推測に基づくものであり、正確な情報は存在しません。
鉄の強度=武器の強さ
たかだか鉄の純度が違うだけでそんなにも大きな差が出るものだろうか。もちろん、その点について疑う方も多いだろうと思う。
実際、剣などの武器に使われるのは鉄と言っても、より強度を高めるよう加工された「鋼鉄」である。
鋼鉄は、鉄の中に少量の炭素を混ぜることでその強度を増している合金の一種だ。
鉄は鉱石の状態から高熱によってドロドロに溶かし、不純物を取り除いた後、型に入れ、冷やし固めて鋳造する。
このままの状態だと、鉄は思いのほか脆い。
何かの力が加わったとき、物体が元に戻ろうとする特性を「可塑性」と呼ぶが、大した加工も施していない鉄はこの「可塑性」が低いために、例えば他の剣と打ち合わせてしまったとき、衝撃に耐え切れず折れてしまうのだ。
例えば日本刀でも知られる、金属を火にくべて叩く「鍛鉄」という技法のように、様々な加工を行うことによって、強度・可塑性を高めていく必要がある。
そうしなければ、実際の戦闘では簡単に破損してしまう。
手持ちの武器の破損という事態は、持ち主の命の危険とほぼ同義だ。
だからこそ腕の良い鍛冶職人というのは重宝される。
先にあげた日本刀でも、五郎入道正宗、長曽祢虎徹といった刀工の作は、武士の世であれ現代であれ、求めるものが多く存在する。
技術には価値があるのだ。
産業革命時代レベル!? 脅威の鉄純度
当然、「ウルフバート」も鉄の強度が非常に高い。では、一体どのくらいの強度を誇るのだろうか。
驚かないで聞いてもらいたい。
この剣が作られたとされるのは、西暦1000年代とされている。
にもかかわらず、この剣の鉄の純度はその当時の水準をはるかに超え、
最も近い鉄純度は、産業革命当時のそれである。
産業革命は18世紀半ばから19世紀初頭にかけて起こった、
「工業化」という工場制機械工業が成立し、機械による高品質の工業製品の量産という、人類史において大きな発展を遂げた出来事である。
名剣「ウルフバート」は、産業革命の800年以上前に、すでに恐ろしいほどの純度の鉄で作られていたのである。
本来、その時代にあることが不自然なほど高い技術で作られた品々を「オーパーツ」などと呼ぶが、「ウルフバート」は紛れもないオーパーツのひとつと言えるはずだ。
失われた鍛鉄技術と謎の金属たち
ウルフバードの鍛造技術については、詳細な情報はほとんど残されていません。しかし、ウルフバートは非常に高度な鍛造技術を必要とする複雑な形状をしていることから、その製造方法には熟練した鍛冶職人が必要だったことが想像されます。
ウルフバードは、刃の部分に硬い鉄を使用し、柔らかい鉄を使用した背部の部分によって強度を保っています。
このように、鍛冶職人は異なる種類の鉄を使用し、高温で鍛造することによって、刃と背部を組み合わせることができました。
また、ウルフバードの刃の形状や凹凸のデザインは、刃物を鍛造する上での高度な技術が必要だったと考えられます。
このような凹凸は、鍛造中に鍛冶職人がハンマーで打ち込むことで形成されます。
また、刃の部分には複数の層があり、それぞれ異なる鉄の種類で構成されていることが分かっています。
しかしながら、ウルフバートがいつ、どのように鍛造されたかについては、現代の技術や知識では解明することができていません。
謎が多いウルフバードの製造技術
「ウルフバート」がどこでどのように生産されたのかは不明である。現在までに171振りの「ウルフバート」が発見されているものの、その中でも本物とされるものはほんの数点であるため、今後の発見とそれに伴う研究で明かされることになるだろう。
今回は「ウルフバート」の材質を例に挙げたが、ある時点で異常なほどの技術水準を持つ金属は、過去の様々な文献などに登場している。
例えばインドのダマスカス地方で作られたとされる、「ダマスカス鋼」もしくは「ウーツ鋼」と呼ばれる特殊な鍛鉄がある。
「ダマスカス鋼」の表面には特徴的な波紋が浮かび、この金属で作られた刀剣は凄まじい強度と切れ味を誇るとされた。
しかし、今ではこの「ダマスカス鋼」の精錬技術は失われ、様々な科学者が再現を試みる“幻の金属”とされている。
ゲームなどでも馴染み深い「オリハルコン」と呼ばれる金属も、過去に実在したとされる金属だが、これも製法が失われている。
文献からの研究により、真鍮を使った合金ではないかという説が有力だ。
日本にも「ヒヒイロカネ」と呼ばれる謎の金属が存在する。
これはもはやどのような金属だったかさえ解らないが、驚異的な熱伝導性を誇り、硬くて錆びない合金であったとされる。
失われた技術。
その言葉にはどこか不思議なロマンティシズムがあるように感じられる。
それは人が造ったもの
一般的に、ウルフバートは勝利のシンボルであり、所有者に力と成功をもたらすと考えられています。また、それが具体的にどのように機能するのかについての詳細な説明は、伝説に基づく解釈に過ぎず、科学的な根拠に基づくものではありません。
製法が失われたにせよ、正体不明であるにせよ、かつてそれらを製造する技術を有していた人類が存在したことは確かだ。
その技術を手に入れるため、自分自身の腕を磨き、新しい知識を積極的に取り入れ、自分の仕事に前向きに取り組んだからこそ、伝説となるような偉業を、かつての人類は達成したのだと筆者は信じたい。
我々も同じ人類として彼らに習い、より高みを目指したいものである。
例え彼らの成した偉業にすら、今は手が届かないとしても。
